第二章 無職透明号 (続き)
七
「いままでsuicideしようと思ったことある?」と抗鬱薬を水で飲みながら三竹君。
「あるよ、ザリガニ釣りをしたこともある、夢精したこともある、ただモスラの卵を見たことはない」とテレビを付けながら吾輩。
「こんなウルトラ級の残酷世界にいながらsuicideの誘惑に駆られたことがないやつは頭が狂ってる」と三竹君。
「またポジ馬鹿の悪口言うのは止してくれよ、飽きたから、みんな頑張ってるんだよ」と吾輩。
「なまじ頑張るから厄介なんだよ、しかしポジ馬鹿は気に入った、語感的にマスコミが流行らせてもおかしくないね」と三竹君。
「黒柳徹子だ、ひさしぶりに見たよ、まだ生きてたんだね」と吾輩。
「テレビはうるさいだけだ、陽気な笑い声が大嫌いなんだ俺は、消してくれ」と三竹君。
「うん」とテレビを消しながら吾輩。
「もっと暗い番組を作ればいいのに、生きるのが嫌になるような番組を、明日から会社に行く気なんか失せるような番組を、明日の結婚式をキャンセルしたくなるような番組を、世界はきょうも安定して残酷じゃないか、いまこうしてる間もガザ地区は地獄だし、拷問されて苦しみもがいているやつもいる、失業して首を吊ろうとしているやつもいる、鬱病がひどすぎて何を食っても砂を噛むような感じしかしないやつもいる、学校のいじめがきっかけで拒食症になった子供もいる、この世界を肯定できる理由など一ミクロンも存在しない、どうして人々はもっと絶望的な顔をして生きないのだろう、朝起きるたびに泣かないんだろう、俺はむかしからそのことがずっと不思議だった」と三竹君。
「寝る前にプロレスごっこでもしようか」と服を脱ぎながら吾輩。
「いいね」と服を脱ぎながら三竹君。
六〇分間、いままさに苦しみの渦中にある全ての人々のことを思いながら吾輩たちはフルチンで闘った。そしてバタンキューした。
八
喉の渇きで目を覚ました吾輩はトランクスをはいて時計を確認する。午前二時一〇分。三竹君はフルチンで熟睡中。しかしなんというかやはり地の文は苦手である。面倒くさい。だいいち退屈だ。だから早く会話文に入ろう。三竹君には悪いが起きてもらう。
「ねえねえ、そろそろ出るよ、もう俺はすっかり回復した、あんまり長くいると延長料金が加算されるよ」と彼を揺り起こしながら吾輩。
「ううううん、日銀のマイナス金利解除はいったいいつなんだ?」と眼をこすりながら三竹君。
「知らないよ、もう出よう、朝勃ちなんかしてる場合じゃない、早く服を着てくれ」と吾輩。
「わかった、さいきんエクアドルがコカインの密売拠点になっていて、ギャング同士の抗争とかで、治安がやたら悪化しているらしい、このまえ拷問の物凄いグロ動画をみた、人間の残忍性には限りが無いよ」と三竹君。
「君そんなことばかり考えているから鬱になったんじゃないの?」と吾輩。
「いや逆だよ、鬱だからこそそんなことしか考えられないんだ」と黒のボクサーブリーフをはきながら三竹君。
「これからどこ行く?」と吾輩。
「とりあえず210号線を走破しよう、行き先を考えるのはそれからだ」と黒のデニムパンツをはきながら三竹君。
「そうだね、俺はもう家には帰らない、母親の顔も父親の顔も見たくない」と吾輩。
「親ってのは利用するためにこそ存在してるんだけど、ほとんどのアホはそのことに気が付いていない」と黒のタンクトップを着ながら三竹君。
「利用って? 金蔓とか?」と吾輩。
「そう、あいつらは俺の微々たる快楽を最大化させるための一つの手段に過ぎない、蹴り倒さないだけでも親孝行と思いやがれってんだよ」と黒のパーカーを着ながら三竹君。
「どんなけ恨みに思ってんだよ」と吾輩。
「俺をこんな地獄にちょくせつ叩き落とした奴らを許せるはずがないじゃないか、許せているやつらの方がどうかしてるんだ、俺の怒りは俺の理性がマトモな証拠だ」と黒の靴下をはきながら三竹君。
「まあ分からなくもないけど、やや執念深過ぎる気もする」と吾輩。
「お前には俺の心の傷は分からない、人間がこの世に生まれて来ることそのものが外傷体験なんだというオットー・ランクの説を俺は支持してるよ、こんど彼の本を貸すよ、読んでみな、ところで料金はいくらなんだ?」と財布を取り出しながら三竹君。
「二一〇円」と吾輩。
「安すぎないか?」と三竹君。
「ハイパーデフレーションのせいだよ」と吾輩。
「はじめて聞いた、なんか食いたいね、吉野家だな、あそこの豚丼は最高だ」と三竹君。
「君は動物の肉を食うことは平気なのか? それも子作り同様、けっこうヤバいことだろ?」と吾輩。
「その議論は長くなるからまたあとでやろう、このいい加減な連載はまだ終わらないんだろ?」と三竹君。
「たぶんね」と吾輩。
吾輩たちはハワイアンを出た。
九
「抑鬱が強すぎてもうだめかもしれない、息苦しい」と抗鬱薬をアクエリアスで飲みながら三竹君。
「どうする? もう帰ろうか?」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹
「そんなこと言うなよ」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「生きていればいいことがある」と三竹君。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「豚丼食べよう」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「豚丼にはたっぷり七味唐辛子をかけよう」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「そのあとは映画に行こう、ピート武の新作を見よう」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「そのあとは東珍坊でも観光しよう、あそこの眺めは綺麗だよ」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「そのあとは大型書店でも行こうよ、君のおすすめの本の話をたっぷり聞かせてくれ」と吾輩。
「もう身罷りたい」と三竹君。
「やっぱ帰る?」と吾輩
「帰っても地獄だ、隣のジジイの音に俺は苦しめられている、どこにも安らげる場所がない」と三竹君。
「そろそろ国道210号線が終わるよ、ほらあそこに終点の看板がある」と吾輩。
「ちょっとは良くなってきた、心配させて悪かった、君には本当に感謝してる、俺たちの友情は永久に不滅だ」と三竹君。
「嵐はいずれ過ぎ去るよ、そろそろ市街地だ、飯にしよう」と吾輩。
「うん」と三竹君。
十
国道210号線の終点直前、とつぜん三竹君は吾輩からハンドルをうばって右に急ハンドルを切った。対向車線には大型観光バス。モウマニアイソウモナカッタ。<完>
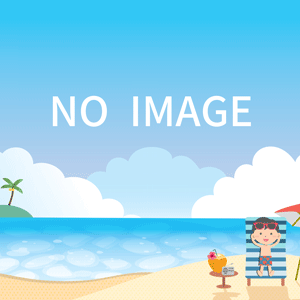
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。