第一章 旅立ち
一
吾輩はニートである。名前は小野塚文雄である。年は三十。増税メガネとは呼ばないでほしい。
吾輩、どこで生まれたかはそれなりに見当は付いているが、そんなことはさしあたりどうでもいいのである。それより退屈なのでこれから家の周辺でもぶらぶら歩いてみることにしよう。いま家に母親がいてうるさいのである。口を開けば働けだのいつまでも養えないだのぶつぶつこぼしまくるものだからいい加減うんざりしているのである。いったいどうして親という人種はこうわがままなのだろうか。這えば立て立てば歩けの親心なんていうがいつもそんなに都合よくいくと思ったら大間違いである。頼んでもないのにこんなにだるい世界に吾輩を産み落としたのだからせめて大人として最後まで面倒くらいはみてほしいものだが、吾輩のこうした全うな論理はこの世界ではあまり評判がよくないようである。「ペットは最後まで責任をもって飼いましょう」とみんな幼少の頃に教わったはずである。いいかげんみんな大人になってほしいものである。って吾輩はペットじゃない!
二
ニートは孤独である。わけても平日の昼間は絶望的に孤独である。大の大人というのは平日の昼間になんの目的もなしにそのへんをうろうろしていてはいけないことになっている。すくなくとも吾輩の住むヌッポン国ではそうである。そういうことだから吾輩はふだん日中はめったに出歩かない。出歩くのはきまって深夜である。しかるに今日はまだお日様が高いうちから吾輩は出歩こうとしている。これが冒険でなくてなんだろう。男子たるものつねに危険と隣り合わせで生きなければならぬ。男は敷居を跨げば七人の敵がいるらしいが、吾輩の場合は家にも敵がいる。口やかましい母親と昭和脳人間の父親である。この凡庸で小汚いつがいを見ていると吾輩は生きるのがますます嫌になってくる。結婚生活という究極の悪趣味に我慢できれば人間はほかのどんなことにもきっと我慢できるに相違ない。ああ人生は修行である。
三
吾輩はいま近所のアケボノ公園にいる。幼稚園児でいっぱいである。なにがなんでも滑り台を逆走したがっている男の子をながめていると、吾輩にもこんな時代があったのだとつい感傷に浸ってしまうが、きっとあの子らのなかにも将来のニートがいるのだと思うと感傷にばかり浸ってはいられないような気がしてくる。吾輩はあの子らの十年後二十年後を想像してみる。二〇四〇年には三人に一人は六五歳以上になるとかいうそんな陰鬱きわまる記事をきのう吾輩は読んだ。子供という名の拉致被害者がだんだん少なくなっていくのはまことに歓迎すべきことではあるが、年寄りばかりがやたらに増えまくる世の中というのはあまり歓迎できない。好奇心はちきれんばかりの吾輩としては老人大国ヌッポンのグロテスクな末路をこの目でみたいとは思うが、当事者としてその末路にかかわるのは御免である。どうしましょう。どうしましょう。
四
ガキどもいや子供たちはもういなくなっている。いるのはミニチュアダックスフンドを散歩させている小太りの老婆だけ。ああいう純粋な愛玩用動物はいったいいくらで売買されているんだろう。ちょこちょこ歩いている犬を見ているとむしょうに腹がたってきた。吾輩はさっきコンビニで買った氷結無糖レモンのロング缶を開け一気に飲み干す。酒は昼間の公園で飲むに限る。反逆者になった気になれるから。世間のくだらない常識への反逆だ。これで職務質問なんかあればいい肴になるんだが。吾輩はなぜか急に瞑想したくなったのでしばらく瞑想した。
五
眼を開けると前にはさっきの小太り老婆がいた。「ねえあなた、ジャイアントパンダの出産って見たことある?」「ありませんね」「そう残念ね、すごいのよ」。老婆は香水の匂いだけを残して去って行った。
六
吾輩はいま市立図書館にいる。読みたい本などがあるわけではない。というか吾輩はがんらい活字というものをひどく苦手にしている。あんなインクの染みの列なりを何時間も飽きずに見続けられる人たちには驚きを禁じ得ない。一種の変態趣味と言うべきではないか。
しかし平日だというのにあんがいに人がいる。ほとんどジジババだ。まるで老人ホームじゃないか。吾輩と年の近そうな「若者」はなかなか見つかりそうもない。と思ったらいた。難しそうな顔をして難しそうな本を読んでいる。やはり小説というのは都合のいいときに都合のいい人物を召喚できるからいい。よく見るともうすでに三十五は超えていそうだ。いやことによると四十を超えているかも知れない。とはいえこの老人大国ヌッポンにあっては四十代でさえまだ「若者」なのである。声を掛けるべきか掛けざるべきか、それが問題だ。男は危険と隣り合わせで生きなければならぬ。吾輩はその「若者」に近寄った。「あの、ジャイアントパンダの出産を見たことはありますか?」
七
男は怪訝な目で吾輩をみた。「見たことはありませんね」と彼。「見たいですか?」と吾輩。「見たいとは思いません」と彼。だんだん険悪な顔つきになってきた。「何を読んでいたんですか?」と吾輩。彼は本の表紙を吾輩に向けた。デイヴィッド・ベネター『生まれてこないほうが良かった』。「それはどんな本ですか?」と吾輩。「存在してるだけで人はぜんいん不幸だってことを論理的に主張してる本」と彼。「どうしようもないですね」と吾輩。「うん」と彼。「あなたは生きるのを止めたい派の人間ですか?」と吾輩。「うん」と彼。「とりあえずそのへん歩きませんか? 僕には友達がいないんですよ。よければ友達になってください」と吾輩。「うん」と彼。
八
吾輩たちはいまニートリという家具店にいる。吾輩の年収ではとても手の届きそうにないダブルベッドなどを眺めているうちだんだん気鬱が強くなってきたので、吾輩は新しくできた友達に名前を聞くことにした。「三竹三郎」と彼。「僕は小野塚文雄」と吾輩。「なんて呼べばいいかな?」と彼。「増税メガネ以外ならなんでもいいよ」と吾輩。「じゃあサトシってのどう?」と彼。「OK、三竹君のことは何て呼べばいい?」と吾輩。「なんでもいいよ」と彼。「じゃあハジメってのはどう?」と吾輩。「OK」と彼。
九
ニートリでは何も買うものがなかったので吾輩たちは店を出ていま春の河川敷を歩いている。
「ところで増税メガネさあ、おまえ何歳なの?」と彼
「いやそう呼ぶなってさっき言ったじゃん」と吾輩。
「ごめん、相手の嫌がることをやったら距離が縮まるかなと思って」と彼。
「縮まらないよ、君ぜったい友達つくれないタイプでしょ」と吾輩。
「お前もいないくせに」と彼。
「年は三十だよ、君は?」と吾輩。
「何歳と思う?」と彼。
「年齢当てクイズは嫌いだから早く答えろカス」と吾輩。
「お前も一気に詰めてくるね、二十八だよ」と彼。
「嘘つくなって、どう見ても俺より年上じゃん、肌の感じからして」と吾輩。
「いや本当だよ、疑うならマイナカード見せるけど?」と彼。
「いや、いいよ」と吾輩。
「いやその眼は疑ってる、見てくれよ」と彼はポケットから財布を取り出し、カードを提示した。記された生年月日から計算して確かに今年で二十八らしい。
「俺が三十であることの証拠も見せようか?」と吾輩。
「いやいいよ、疑ってないから」と彼。
「いやその目は疑ってる、見てくれ」と吾輩は財布を取り出し運転免許証を水戸光圀の印籠のごとく提示した。
「おまえ自動車を運転できるのか?」と彼は吾輩を見つめる。
「まあね、たまに親の車を運転するていどだけど」と吾輩。
「俺は持ってない」と彼。
「なんで?」と吾輩。
「みんなが取ってるから、みんなと同じ事をしたくないから」と彼。
「それだけの理由?」と吾輩。
「自分の運動神経をぜんぜん信用してないんだ」と彼。
「だいたい年間三千人近くは交通事故で身罷っているとかいうね」と吾輩。
「俺は人を轢きたくないし轢かれたくもないね、ところでなんで突然そんな上品な言葉を使うんだ?」と彼。
「そうでないと管理人の決めた禁止ワードに引っかかるんだよ、あと俺は労働とは無縁の貴族だからときどきこんな言葉を使いたくなるんだ、でもこの時代にあっては運転免許証を持ってないとかなり不便だろ?」と吾輩。
「不便よりも恐怖のほうががずっと強い」と彼。
「こんど優雅にドライブでもする? 俺は法定速度はちゃんと守るから、こんな平日の昼間に外をぶらぶらできるんだからどうせ無職でしょ」と吾輩。
「無職だからって暇なわけじゃない」と彼。声にちょっと怒気がある。
「ふだん何してるの?」と吾輩。
「読書、思索、執筆、散歩、手淫」と彼。
「何を書いてるの? まさか小説とか?」と吾輩。
「詩みたいなもの」と彼。
「詩みたいなもの? こんど読ませて」と吾輩。
「絶対に貶さないならいいよ、俺はこうみえて豆腐メンタルだから」と彼。
「貶すも貶さないも、俺は文学なんかぜんぜん知らないから批評できない」と吾輩。
「文学なんか陰キャの趣味だよな、俺もほんとうはもっとワイルドな趣味を持ちたいよ、ハーレーダビッドソンなんか乗り回したりして、でもカネないし」と彼。
「カネのかかる趣味しか持てないやつはバカだって、どこかのネット掲示板の元管理人が言ってたよ」と吾輩。
「それを言ってもダサくないのはカネのある奴だけだよ、貧乏人が言ってもヒガミにしか聞こえない」と彼。
「ダサいとかダサくないとかを気にしてるほうがダサくない?」と吾輩。
「そんな少年漫画のセリフみたいなことをドヤ顔で言えてしまうお前もダサい」と彼。
「人目なんか気にしないで生きようよ、ゴーイングマイウェイさ」と吾輩。
「そんなのはポエムに過ぎない、人間はどこまでも社会的生物だから他人からの眼差しを逃れることは出来ないんだ、人目を気にしなくなったらそれはたぶん怪物だ、たぶん路上でオナニーなんか平気でやるんじゃないか」と彼。
「それは極端だ」と吾輩。
「いや極端じゃない、俺はこの問題についてはたぶんお前よりもずっと長く考えている」と彼。
もうかなり薄暗くなっていた。そろそろ帰宅しようか、ということになった。吾輩はひさしぶりに発声器官を長く使ったのですっかり疲れていた。ただそれは悪い疲れではなかった。
十
家に戻ると母親と父親が怒鳴り合っていた。吾輩は廊下で耳を澄ませる。
父親「✕〇〇△お前の育て方が悪いからあいつは〇✕△✕✕✕△◇〇✕✕」
母親「△✕いまさらそんなこと言っても〇〇△◇✕✕〇〇〇✕✕✕」
父親「✕△だいたいいつまであんなに甘やかして✕✕✕✕〇〇〇△」
母親「でも半分はあなたの遺伝子✕✕✕△△〇〇〇〇」
吾輩は服を脱いでパンツを脱いで裸になった。そして喧嘩の渦中に飛び込んで旋回的に舞い続けた。一時間、二時間、三時間・・・恍惚と忘我。とちゅうから母親と父親も裸になった。三人とも手をつないで舞い続けた。疲れなど微塵も感じなかった。ただ三人とも泣きまくっていた。全身のすべての水分を涙にして。
気が付けば朝の七時になっていた。床は涙の海だった。サザンの「涙の海で抱かれたい」を口ずさむ余裕など吾輩たちには無かった。
「もうこの家には住めないな」と全裸の父親。
「そうね引っ越しましょう」と全裸の母親。
「安い賃貸アパートでも探そう」と全裸の父親。
「そうね」と全裸の母親。
「文雄、お前はどうしたい?」と全裸の父親は吾輩の眼をみる。
「俺はもうお前たちみたいな腐れ夫婦とは暮らしたくない、今日から世界を放浪したい、旅費をくれ」と全裸の吾輩。
「自分で稼ぎなさいよ」と全裸の母親。
「そうだ、だいたい誰のおかげで生きていられると思ってるんだ」と全裸の父親。
吾輩はもうこれ以上なにを言っても無駄だと観念し、服を着て、家を出た。
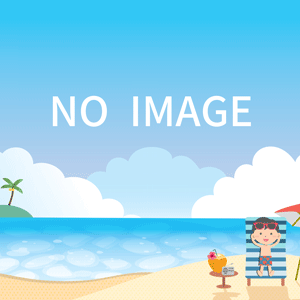
コメント
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。